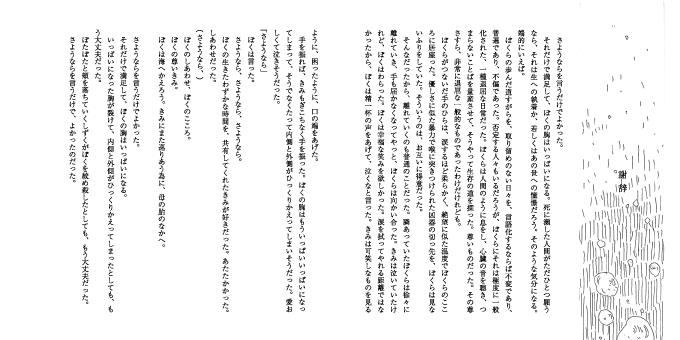A面/『ボーイミーツガール 顔のない天使』
あたしのことなんて忘れてよ。雑多な色にまみれた色紙の寄せ書きの宛名とか、卒業アルバムの色あせた写真とか、発表会の目録の素っ気ない活字で書かれた名前とか、そんなものの中にあたしを見つけたりしないで。あたしの趣味じゃない 下世話な額縁の中から、あたしをどうか連れ去って。もっと美しい定規であたしを計って。藁半紙に印刷された学年順位とか、化粧の上手さとか、プリーツスカートの丈とか、どんな人と恋人なのかとか、そんなありあわせの目盛りにあたしの体を押しつけないで。よく見て。今この瞬間だけが 今君の目に映っているあたしだけが、君にのこるあたしの焼き印となるように。手紙も上手に書けなかった。自分の書く字が嫌いだから。代わりに君が美しいと言っていた顔をよく見て。この日のために買った白いスカートの裏地は青ざめた肌のように淡く透明な藍色。ちょうど今、朝焼けにかき消されそうな星座のような。風をうけて口を開くフレアスカートは明け方に開く朝顔によく似ているでしょう。君の好きな。ああうつくしい。君を通して見つめていた世界のすべては甘くよろめいている。あたしは思い出している。あたしの美しい世界を思い出している。渇いた校庭や濡れた玄関や焼け落ちそうな夕日のなかに佇む君を。君がわたしに向けたまなざしの意味に知らないふりをして、この完璧な瞬間にすべて閉じ込めてしまえたらなんて楽なんだろうとずっと思ってた自分を。君の細くて長い睫毛の奥の、青みがかった黒い瞳に映る自分が、まだ綺麗なうちに、損なわれてしまわないうちに、すべておしまいにしましょう。ねえだから、さようなら、あたしの美しい世界。(空をあおげば、きみのまなざしが望んでいたままの温度であたしへとおりてくる。あたしはそのときはじめて、生きる意味を知った。)
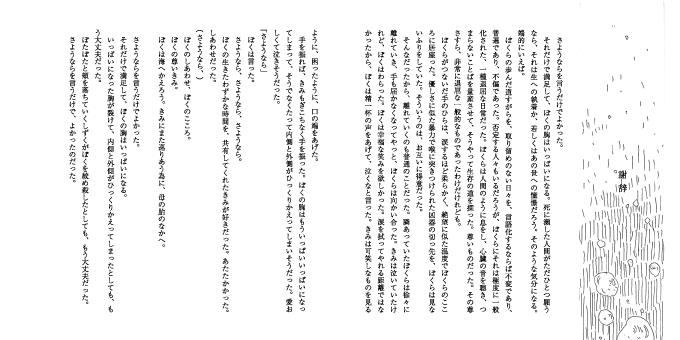
B面/『謝辞』
さようならを言うだけでよかった。
それだけで満足して、ぼくの胸はいっぱいになる。死に瀕した人間がただひとつ願うなら、それは生への執着か、若しくはあの世への憧憬だろう。そのような気分になる。端的にいえば。
ぼくらの歩んだ道すがらを、取り留めのない日々を、言語化するならば不変であり、普遍であり、不偏であった。否定する人々もいるだろうが、ぼくらにそれは極度に一般化された、一種退屈な日常だった。ぼくらは人間のように息をし、心臓の音を聴き、つまらないことばを量産させて、そうやって生存の道を探った。尊いものだった。その尊さすら、非常に退屈な一般的なものであったわけだけれども。
ぼくらがつないだ手のひらは、涙するほど柔らかく、絶望に似た温度でぼくらのこころに居座った。優しさに似た暴力で喉に突きつけられた凶器の切っ先を、ぼくらは見ないふりをしていた。そういうのは、お互いに得意だった。
そんなだったから、離れていくのも普通のことだった。隣あっていたぼくらは徐々に離れていき、手も届かなくなってやっと、ぼくらは向かい合った。きみは泣いていたけれど、ぼくはわらった。ぼくは幸福な笑みを欲しかった。涙を拭ってやれる距離ではなかったから、ぼくは精一杯の声をあげて、泣くなと言った。きみは可笑しなものを見るように、困ったように、口の端をあげた。
手を振れば、きみもぎこちなく手を振った。ぼくの胸はもういっぱいいっぱいになってしまって、そうでなくたって内側と外側がひっくりかえってしまいそうだった。愛おしくて泣きそうだった。
「さようなら」
ぼくは言った。
さようなら、さようなら、さようなら。
ぼくの生きたわずかな時間を、共有してくれたきみが好きだった。あたたかかった。しあわせだった。
(さようなら、)
ぼくのしあわせ、ぼくのこころ。
ぼくの尊いきみ。
ぼくは海へかえろう。きみにまた巡りあう為に、母の胎のなかへ。
さようならを言うだけでよかった。
それだけで満足して、ぼくの胸はいっぱいになる。
いっぱいになった胸が裂けて、内側と外側がひっくりかえってしまったとしても、もう大丈夫だった。
ぽたぽたと頬を落ちていくしずくがぼくを絞め殺したとしても、もう大丈夫だった。
さようならを言うだけで、よかったのだった。
『A面/B面』
2012/11/18 初版
A面 31頁/B面 39頁 120×120mm